文学部を選んだ理由
学部別在学生インタビュー(大学案内2026)
2025/05/07
立教を選ぶ理由
OVERVIEW
文学部に所属する在学生にそれぞれの学科を選んだ理由などを聞きました。
文学部キリスト教学科4年次 八色 千夏さん(東京都 東大和南高等学校)

キリスト教を学ぶことで世界を多角的に見る視点が身についた
私がキリスト教学科を志望した理由は、世界史を学ぶ中で宗教の重要性を強く感じたからです。宗教は歴史の転換点や個人の行動基準に影響を与えていますが、現代社会においてもその役割は変わりません。そこで、特に世界最大の宗教であるキリスト教について深く学びたいと思いました。キリスト教学科では、キリスト教と政治、メディア、アートなど、キリスト教に関連することならなんでも学ぶことができます。例えばジェンダーをテーマとした講義では、現代社会で顕在化している性別による権利や待遇の差別を巡る問題の端緒を、ヘブライ語の「女性」を表す文字の由来や、聖書における女性の誕生の描写などを通じてあぶり出していきます。
以前は「善悪」「是非」といった二項対立で物事を判断することが多かったのですが、こうした学びを通じて、それぞれの背景や事情を踏まえ、より複雑な視点で多角的に見る力を得ることができたと感じています。将来は、世の中を便利にするサービスや製品の開発に携わりたいと考えていますが、キリスト教学科で培ったこうした姿勢は、この夢の実現に大いに役立つと確信しています。
文学部文学科英米文学専修4年次 ウォーカー・ジェイコブ・スコットさん(The Henley College)

人間や社会のあらゆる側面に影響を与える言語学の奥深さ
英米文学専修に入学した理由は、教職を目指す中で母語の専門知識を深めたいと考えたからです。授業では英米文学の名作やその内容、背景の知識、構造上の特徴だけでなく、音節や強弱のアクセントといった英語独自の韻律などの表現方法に触れることで、日本語訳で読むだけではなかなか理解できない深みを得ることができます。また、英語がどのように成り立っているかといった言語学的な視点でも学ぶこともできます。現在は標準英語というテーマを、イギリスに限定して考察しています。そのなかでイギリス固有の容認発音という標準英語が実際には方言として機能していることを知り、具体的にイギリスのメディアの例を挙げて、この視点を研究しています。「標準語と方言」の関係ではなく、「標準語が方言である」という新しい視点が興味深いと感じています。
言語学は単に「言語」を学ぶ分野だと思われがちですが、実際には言語が人間と社会のあらゆる側面に与える影響について学ぶことができます。将来的には教職に就き、音声学を通じて、英語を複雑だと思っている生徒たちに理解してもらい、成り立ちや知識で、英語を学びやすい環境を提供したいと考えています。
文学部文学科ドイツ文学専修4年次 浅見 友香さん(群馬県 高崎女子高等学校)

ドイツ近代文学から、女性が活躍できる社会の実現を模索
英語や文学への関心や、倫理の授業で学んだドイツ哲学者への興味から、新たな視野を広げる挑戦としてドイツ文学を選びました。また、立教大学は学科の枠を超えて授業を受けることができるため、ドイツ文学に加えてさまざまな学科の授業も積極的に受けました。現在はジェンダー研究を取り扱うゼミに所属しており、ドイツの近代女性の労働環境や日本女性の社会進出に関する研究と卒業論文の制作に取り組んでいます。女子校出身の経験から、女性男性というジェンダー概念に関係なく個人が活躍できるような社会の実現について興味があり、ドイツの近代史や近代ドイツを舞台にした小説から当時の女性のあり方や、社会においてどのような存在として認識されているのかを学び、個人が活躍できる社会の実現可能性を模索しています。
将来は、女性が自分のキャリアについて積極的に考えられるような社会を実現する手助けができたらと考えています。大学卒業後は人材関係の会社で働くので、ドイツ文学の研究から得ることができた、さまざまな立場の視点で物事を捉える姿勢を忘れず、多種多様な人と関わり、自分の経験を積んで自分の目標に生かしていきたいと思います。
文学部文学科フランス文学専修4年次 菅原 凜さん(神奈川県 横浜栄高等学校)

フランス文学や文化に触れることで私生活でも視点が大きく広がりました
フランス文学専修では、文学から歴史まで幅広く学ぶ機会があります。特に思想や哲学の授業では、普段とは異なる視点から物事を捉える力が培われ、実生活においても新たな楽しさを見つけることができます。言語の習得だけでなく、フランス文学や文化を通じて、考え方が広がる貴重な体験をしてきました。
私の研究テーマは、フランス文学における詩的イメージです。特に、卒業論文では詩的イメージと境界について研究しており、詩の抽象的な表現が意識と無意識、生と死のような境界をいかに溶解させるかについて分析をしています。必修科目以外にもフランス語のニュース記事を読んだり、フランス文学を原文で学ぶ講義など、実践的なフランス語を楽しく学ぶこともできます。今はフランスの政治などにも興味があり、これらの学びが海外世界へ視点を向けるよいきっかけになったと感じています。また、たくさんの国の人たちと関わっていきたいと思っており、多様な言語を学ぶきっかけにもなりました。
今後は、フランス語や文化の知識を活かし、輸入食品のバイヤーとして食品関係の仕事に携わりたいと考えています。食べることへの興味を軸に、フランスの豊かな食文化に関われたらと考えています。
私の研究テーマは、フランス文学における詩的イメージです。特に、卒業論文では詩的イメージと境界について研究しており、詩の抽象的な表現が意識と無意識、生と死のような境界をいかに溶解させるかについて分析をしています。必修科目以外にもフランス語のニュース記事を読んだり、フランス文学を原文で学ぶ講義など、実践的なフランス語を楽しく学ぶこともできます。今はフランスの政治などにも興味があり、これらの学びが海外世界へ視点を向けるよいきっかけになったと感じています。また、たくさんの国の人たちと関わっていきたいと思っており、多様な言語を学ぶきっかけにもなりました。
今後は、フランス語や文化の知識を活かし、輸入食品のバイヤーとして食品関係の仕事に携わりたいと考えています。食べることへの興味を軸に、フランスの豊かな食文化に関われたらと考えています。
文学部文学科日本文学専修4年次 杉山 心さん(茨城県 土浦日本大学高等学校)

小説から雑誌、ラノベやマンガまで、すべての題材が研究の対象です
幼少期から読書が好きで、日本文学には好きな作家が多かったことと、あるアーティストの歌詞に尾崎放哉の俳句が使われていたことから自由律俳句に興味をもち、より詳しく探究したいと考えてこの学科を選びました。それまでは作品の背景や当時の社会情勢などを考えることはありませんでしたが、学科の学びを通して、書かれた当時の風俗や慣習・生活スタイルを理解しながら研究する方法を考えるようになりました。文豪たちの人間模様などについても情報を収集し、時代の変遷を追いながら「読解」しています。日本文学専修は広範囲で、鳥獣戯画(中世日本)から戦前戦後の検閲の歴史、ラノベの研究に至るまで、時代的・ジャンル的にも多方面に及びます。ゼミ内には、ジャンル・作家の有名無名にとらわれず研究に励む、研究対象への熱意と思い入れにあふれた人が大半です。マンガを題材とした発表を拝聴したときは俳句を研究しているだけでは出合えなかった作品に触れる機会をもつことができました。
将来は、出版社で本に関わる仕事をしながら、自分が宣伝した本を日本中の人々が手元に置いて、インターネットより信頼できる書籍として愛してくれるように働きかけられるような人間になりたいです。
文学部文学科文芸・思想専修4年次 石山 綾香さん(東京都 東京大学教育学部附属中等教育学校)

人はなぜAIを普通の道具とは分けて問題にしたがるのか
高校の倫理の授業で、映画「桐島、部活やめるってよ」を実存主義の視点から分析した際に、自分の見方だけが物事のすべてではないという気づきがあり、より多様な視点から社会を探究したいと思うようになりました。立教大学の文芸・思想専修は、思想を土台に世の中のさまざまな事象について探究できると確信して入学しました。
現在は「AI倫理」をテーマに研究しています。私たちは当たり前にAI活用されたものを道具として使用しているにもかかわらず、AIが「人間の知能の再現」だと認識すると単なる道具とは見なせず、SFの世界では脅威の対象とされたりします。私はAIを通して「人工物=道具」という定義がどのように変化していくのか、AIと人間の関係から人間と道具を捉え直すことができないかと研究しています。
将来的には、一人ひとりの声を拾い、伝える記者になりたいと考えています。アルゴリズムが優しくなり、興味のある情報を簡単に入手できるようになりましたが、それは多様な視点を理解する機会を奪っているのではないかとも感じています。メディアとして多様な声を拾い、異なる興味関心をもつ人々をつなげ、分断のない社会の形成に貢献したいと考えています。
現在は「AI倫理」をテーマに研究しています。私たちは当たり前にAI活用されたものを道具として使用しているにもかかわらず、AIが「人間の知能の再現」だと認識すると単なる道具とは見なせず、SFの世界では脅威の対象とされたりします。私はAIを通して「人工物=道具」という定義がどのように変化していくのか、AIと人間の関係から人間と道具を捉え直すことができないかと研究しています。
将来的には、一人ひとりの声を拾い、伝える記者になりたいと考えています。アルゴリズムが優しくなり、興味のある情報を簡単に入手できるようになりましたが、それは多様な視点を理解する機会を奪っているのではないかとも感じています。メディアとして多様な声を拾い、異なる興味関心をもつ人々をつなげ、分断のない社会の形成に貢献したいと考えています。
文学部史学科4年次 松岡 世菜さん(福岡県 筑紫丘高等学校)

限られた情報の中で新しいことを見つける力が身につく
幼い頃から偉人伝や歴史マンガに興味があり、大学では本学科を志望してヨーロッパの中近世の歴史や文化、芸術を中心に学んでいます。西洋美術に関する授業は古代から近現代までさまざまな授業が開講されていますが、例えばキリスト教美術の授業ではキリスト教伝播の歴史から写本美術、建築様式の変遷など、さまざまな専門性の高い授業が開講されていて、自分の興味関心をとことん突き詰めることができました。また、芸術を作品としてただ鑑賞するだけではなく、社会史と結びつけて考えることでなぜこのテーマが多く描かれているのか、なぜこの技法が流行しているのかなど、当時の社会を考察するための史料として捉える視点を得ることもできました。史学科での学びを通して、こういった物事を多角的に考える力が養われたことが大きな収穫になったと感じています。卒業後はIT系企業に進む予定ですが、限られた情報から必要なことを見つけ出し、文章を構成する力は仕事にもきっと生かせると思います。歴史を学ぶことは人と関わっていく上で重要な教養であると考えているので、これからも美術館や博物館を訪れたり、歴史や芸術に関する本を読むなど、学ぶことを続けていきたいです。
文学部教育学科4年次 福田 大晟さん(神奈川県 川和高等学校)
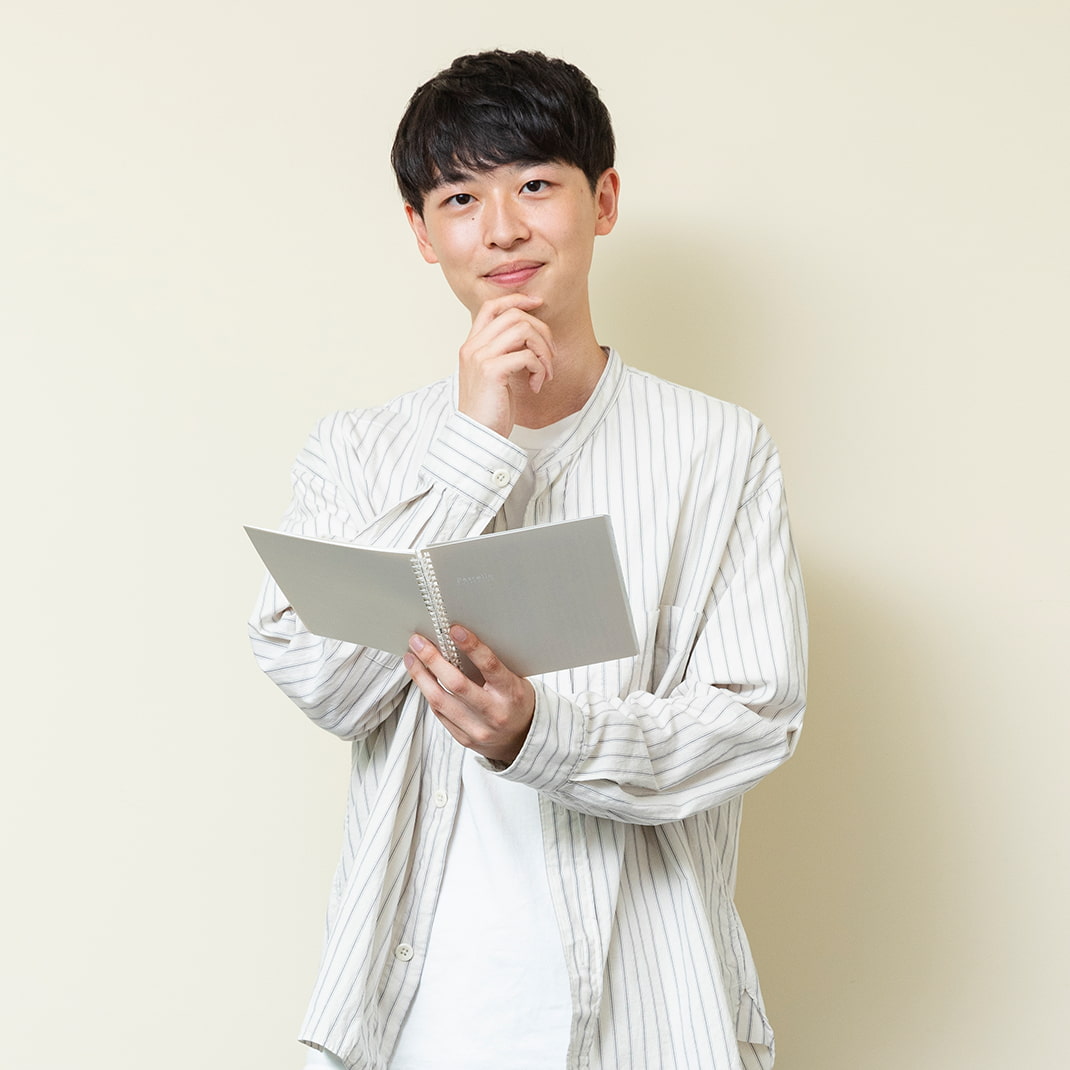
学校教育にとどまらない生きている限り続く『教育』の魅力
教育心理学では人間の発達や学習について代表的な考え方を学び、教育社会学では会話分析をとおして教員と生徒、生徒同士の会話構造を考察しました。また、教育哲学ではメディアや遊びなどさまざまな視点から教育とは何か、教育史では日本の教育制度政策の展開過程を学び、学校教育の意味について考えました。こうしたなかで、学校に入学する前の子どもたちの発達過程から社会人になって就職した職場での学習プロセスまで、教育学は学校教育にとどまらず、私たちが生きている限り関わり続けるものだという学びがありました。
また先生方は話しかけやすい方が多く、授業内、授業外問わず関わりを持ってくださいます。学生はそれぞれの関心事について前のめりになって学ぶ人が多く、講義内のグループワークで熱心に話し合うときには意見交換のなかで新しい考えが生まれることもあります。学科全体の雰囲気が活発なところも魅力だと思います。
将来の目標は、誰もが自分のやりたいことに取り組める社会をつくることです。ヤングケアラーの子どもたちやしょうがい者、情報格差によってやりたいことに取り組めない人々のために、通信系企業でITを活用して、学びの環境を整えることに挑戦したいと考えています。
また先生方は話しかけやすい方が多く、授業内、授業外問わず関わりを持ってくださいます。学生はそれぞれの関心事について前のめりになって学ぶ人が多く、講義内のグループワークで熱心に話し合うときには意見交換のなかで新しい考えが生まれることもあります。学科全体の雰囲気が活発なところも魅力だと思います。
将来の目標は、誰もが自分のやりたいことに取り組める社会をつくることです。ヤングケアラーの子どもたちやしょうがい者、情報格差によってやりたいことに取り組めない人々のために、通信系企業でITを活用して、学びの環境を整えることに挑戦したいと考えています。
CATEGORY
このカテゴリの他の記事を見る
立教を選ぶ理由
2025/05/07
「人」との出会いに恵まれ、「ワクワク」を大切に仕事を選べた
株式会社バンダイ・BANDAI SPIRITS 熊谷 悠岐さん(大学案内2026)